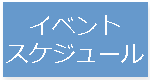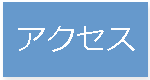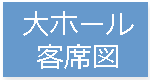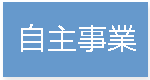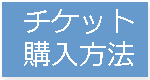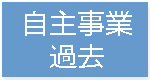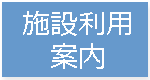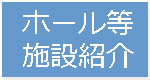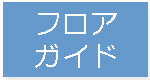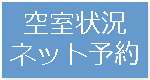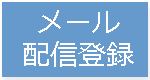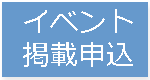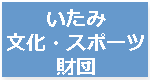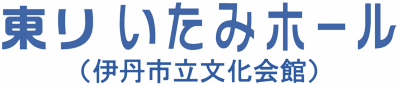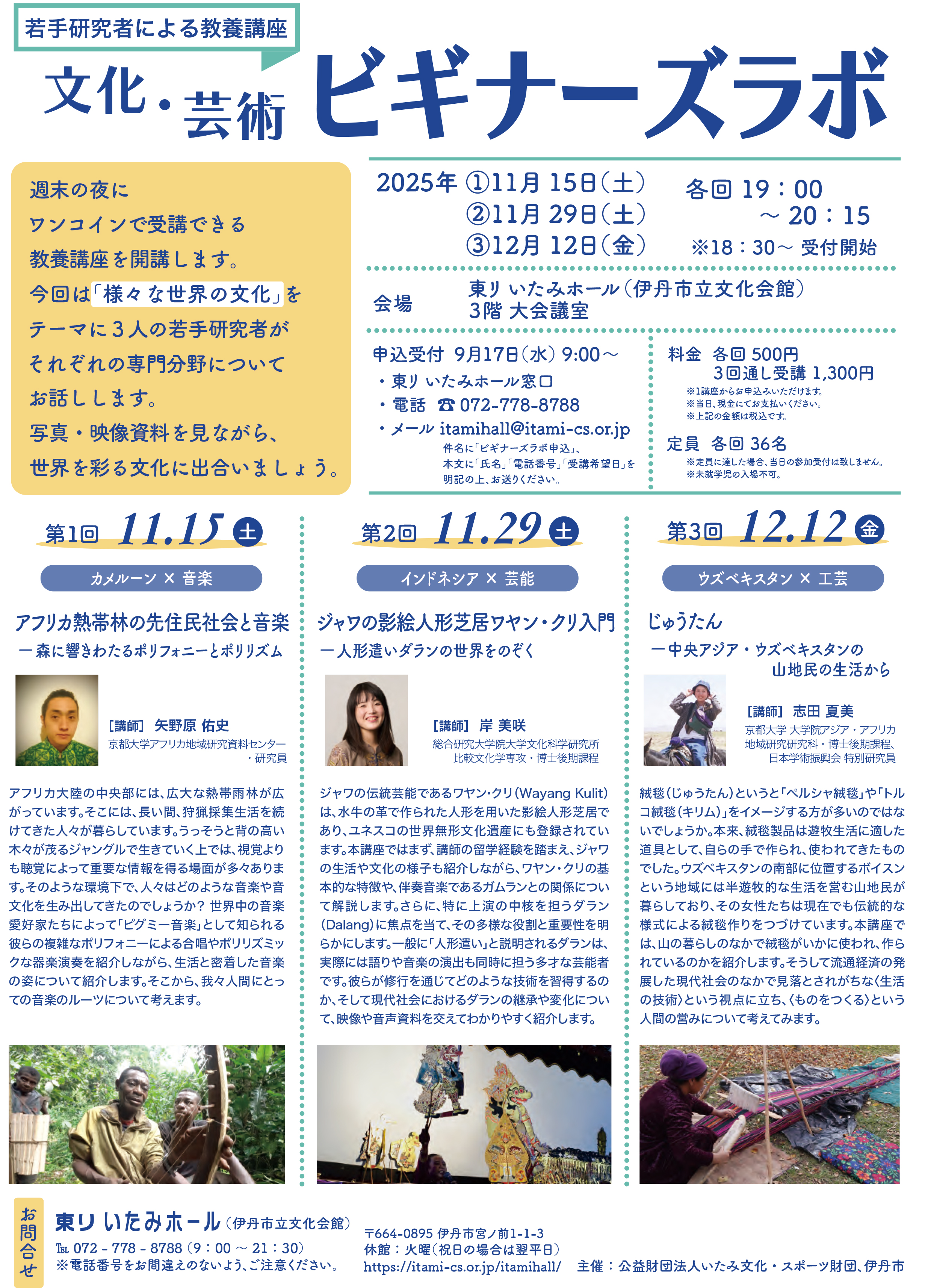若手研究者による教養講座
『文化・芸術 ビギナーズラボ』
終了いたしました。
週末の夜にワンコインで受講できる教養講座を開講します。
今回は「様々な世界の文化」をテーマに、3人の若手研究者がそれぞれ専門分野についてお話します。
写真・映像資料を見ながら、世界を彩る文化に出合いましょう。
【開催日時】
第1回11月15日(土)
第2回11月29日(土)
第3回12月12日(金)
いずれも19:00~20:15(18:30より受付開始・開場)
【会場】3階大会議室
開催日・テーマ・講師・内容
●第1回 2025年11月15日(土)
《カメルーン×音楽》
「アフリカ熱帯林の先住民社会と音楽――森に響きわたるポリフォニーとポリリズム」
講師:矢野原 佑史(京都大学アフリカ地域研究資料センター・研究員)
内容:アフリカ大陸の中央部には、広大な熱帯雨林が広がっています。そこには、長い間、狩猟採集生活を続けてきた人々が暮らしています。うっそうと背の高い木々が茂るジャングルで生きていく上では、視覚よりも聴覚によって重要な情報を得る場面が多々あります。そのような環境下で、人々はどのような音楽や音文化を生み出してきたのでしょうか?世界中の音楽愛好家たちによって「ピグミー音楽」として知られる彼らの複雑なポリフォニーによる合唱やポリリズミックな器楽演奏を紹介しながら、生活と密着した音楽の姿について紹介します。そこから、我々人間にとっての音楽のルーツについて考えます。
●第2回 2025年11月29日(土)
《インドネシア×芸能》
「ジャワの影絵人形芝居ワヤン・クリ入門――人形遣いダランの世界をのぞく」
講師:岸 美咲(総合研究大学院大学文化科学研究所比較文化学専攻・博士後期課程)
内容:ジャワの伝統芸能であるワヤン・クリ(Wayang Kulit)は、水牛の革で作られた人形を用いた影絵人形芝居であり、ユネスコの世界無形文化遺産にも登録されています。本講座ではまず、講師の留学経験を踏まえ、ジャワの生活や文化の様子も紹介しながら、ワヤン・クリの基本的な特徴や、伴奏音楽であるガムランとの関係について解説します。さらに、特に上演の中核を担うダラン(Dalang)に焦点を当て、その多様な役割と重要性を明らかにします。一般に「人形遣い」と説明されるダランは、実際には語りや音楽の演出も同時に担う多才な芸能者です。彼らが修行を通じてどのような技術を習得するのか、そして現代社会におけるダランの継承や変化について、映像や音声資料を交えてわかりやすく紹介します。
●第3回 2025年12月12日(金)
《ウズベキスタン×工芸》
「じゅうたん――中央アジア・ウズベキスタンの山地民の生活から」
講師:志田 夏美(京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士後期課程、日本学術振興会 特別研究員)
内容:絨毯(じゅうたん)というと「ペルシャ絨毯」や「トルコ絨毯(キリム)」をイメージする方が多いのではないでしょうか。本来、絨毯製品は遊牧生活に適した道具として、自らの手で作られ、使われてきたものでした。ウズベキスタンの南部に位置するボイスンという地域には半遊牧的な生活を営む山地民が暮らしており、その女性たちは現在でも伝統的な様式による絨毯作りをつづけています。本講座では、山の暮らしのなかで絨毯がいかに使われ、作られているのかを紹介します。そうして流通経済の発展した現代社会のなかで見落とされがちな〈生活の技術〉という視点に立ち、〈ものをつくる〉という人間の営みについて考えてみます。
受講料 各回500円(税込)、3回通し受講1,300円(税込)
※定員:各回36名
※定員に達した場合、当日の参加受付はいたしません
※未就学児の入場は不可
お申込み方法
東リ いたみホール
●2階事務所窓口来館
●電話予約(TEL.072-778-8788)
〈受付時間9:00~21:30〉
〈火曜休館。火曜祝休日の場合は翌平日休館〉
●メール予約 itamihall@itami-cs.or.jp
件名に「ビギナーズラボ申込」、本文に「氏名」「電話番号」「受講希望日」を明記の上お送りください。
主催:公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団、伊丹市